NEWS
石頭地蔵、オフィシャルインタビューが到着!
2010.02.18
MEDIA INFO

2010年2月17日にニュー・アルバム『carbide』をリリースした、石頭地蔵のインタヴューが到着しました!
地元熊本で夾雑物を排除し、じっくりとインディペンデントな活動を続けてきたフォーピース・石頭地蔵。セカンド・アルバム『カーバイド』は、彼らの磨き上げられたアンプ直結の爆音が冴えわたっている。ポストパンクやニューウェイヴをルーツに持ちながら、決してトラディショナリズムに陥らずノイズやアヴァンギャルド・シーンや現在進行形のポストパンクリバイバルとも共鳴している彼らのアチチュードが発揮されている。拮抗するささくれだった2本のギターにより織りなされるルナティックなアンサンブル。荒れすさんだ心情から虚無感までを残さず捉えるリリック。その乾ききった音の渦にあなたは思わず「Totally Wired!」と叫んでしまうことだろう。
──前作から4年ぶりということですが、ここまでどんな活動をしてきましたか?
芥川勝則(Vocal/Guitar):ファーストができた時点で、『カーバイド』に入っている曲は2、3曲あったんです。そこから曲を作るまでがけっこう時間がかかりました。ローカルの熊本で仕事をしながらマイペースにやっているので、作れないということはなくて、順調に進んだ結果がこれくらい時間がかかるという感じですね(笑)。
──2本のギターの絡みも含め、なかなか一筋縄ではいかない楽曲だと思うのですが、どのようにアイディアをかたちにしていくのですか?
芥川:最初に自分が思い浮かんだフレーズを弾いて、それをベース(高木裕治)に弾いてもらって、ドラム(臼井敏朗)やもうひとりのギター(阿久根哲也)に合わせてもらうんです。シンプルなリフをアンサンブルしていくうちにどんどんずらしてみたり、別のコードのフレーズを乗せてみたりします。好きなことをピックアップしていくよりは、なんとなくちょっと苦手な感じになったなと思うと、変えてもらって、発展させていくかたちです。
──石頭地蔵としての譲れない美学、研ぎ澄まされた感覚が伝わってくるサウンドですが、みなさんにとってかっこよさの定義というのはどんなものなんでしょうか?いわゆるポップソングとしてという意識もないんですよね。
芥川:ないですねぇ。どうしても情緒的なフレーズは排除していくというか。
──そうしたヒリヒリした感じというのは、皮膚感覚としてある?
芥川:フレーズの組み立て方やコード展開によるものだと思います。フレーズを刻んで、普通にパワーコードで作ったり、ユニゾンを使ったりというやりかたはあえてないような組み立て方をします。若干最近はまた考え方が変わってきているんですけれど。
──そうしたバンドのモットーについては、ファーストとセカンドの期間はあってもぜんぜんぶれていないですよね。
芥川:フレージングに関しては、たぶん手癖のようなものがあるからだと思います。メンバーそれぞれのやりたいことがあって、リズムを少し変えたり、曲調はこんな感じでって組み立てていくんですけれど、結果的にどうしてもうちらの音になってしまうんです。
──テレビジョンが引き合いに出されていたりもしますが、活動初期に目指していたバンド像というのはあったのですか?
芥川:特になくて、ワンコードを爆音で延々やって手癖を出し切る、その探り合いみたいなフリーセッションが最初でした。そうした考えが受け入れてもらえたので、活動をはじめて、時間があるときにセッションを続けていて、面白いとは思っていたんですが、はじめは何のビジョンもなかった。でもオリジナルのリフを持っていって、実際に組み立てる作業をみんなでやったら、自分たちなりにうまくまとまったという印象があったので、そこからちゃんとバンドとしてやっていこうとなりました。テレビジョンも最初はコピーしたりしていましたが、個人的にはイギリスのザ・フォールが大好きだったので、ああいう感じでやりたいんですけれど、他のメンバーはまた違う感じが好きだったりすのるで、そこが個性になってきたと思います。
──芥川さんのリスナーとしての原点は?
芥川:高校2、3年くらいかな、パンクはその当時で既に後追いだったんですけれど聴き始めて、そこからニューウェイヴを聴いて。ポップグループとかバースディ・パーティーのようなアグレッシブなポストパンクが好きでした。
──現在の曲作りはちょっと意識が変わってきたというお話がありましたけれど?
芥川:基本は反復をベースにしているので、それが気持ちよさになっていると思いますが、できるだけシンプルにしたいなと思っていました。新作でいちばん新しい曲が「発光カーバイト」という曲で、これがシンプルなエイトビートにシンプルなリフを乗せるというかたちをとっていて、そうしたフレーズを絞っていく方向になった。もちろんこれまでのちょっとずらしていく方法も好きなんですけれど、それよりももう少し演奏する気持ちよさを重視したいなと最近は思っています。『カーバイド』はこれでも多少は音数多いかな、もっとシンプルにできたんじゃないかなという思いがあります。
──「発光カーバイト」はアルバムのなかでも比較的ストレートな印象がありますよね。
芥川:ちょっとリラックスしている雰囲気があると思うので。テンポもそこまで速くないし、ボーカルの乗せ方もいままでにない感じになっていると思いますね。アップテンポな楽曲に言葉数が多いという感じではなく、ゆったりと言葉を乗せられるのは気持ちよかったです。
──リリックについても独特ですよね。意味性やストーリーよりも、シュールな世界が浮かび上がってきます。
芥川:そこは非常に語るのは苦手なところなんですけれど(笑)。結局洋楽コンプレックスが強くて、あからさまに日本語詞で意味が解る言葉を使うのが苦手だったので、あまり良くないことではあるんですけれど、意味の解らない言葉をいろんな本や詩集から引用してわざと解らなくしていく方法をとっていました。当事者としては普通に言葉をただ羅列して、そこから何かが浮かび上がれば、それは聴く人の自由に受け止めてほしい。本来は自分の言葉で自分の言いたいことを表現するのが良いやり方だと思うんですけれど、そこが今後の課題でもあるし、ひとりくらいそういうスタイルの人がいてもいいかなという考えもあって歌詞は考えています。
──文学作品からの影響というのは大きいのですか?
芥川:純文学ですね。ファースト・アルバムの歌詞カードにも書いてあるんですけれど、高村光太郎の言葉や詩は好きです。それだけと言っていいくらい。あとは幸田文の小説は大好きですね。
──地元の熊本で活動されてきて、現在のバンドの周囲の音楽事情はどんな状況でしょうか?
芥川:熊本というより九州の括りで言うと、PANICSMILEとそのイベントから派生して、VELOCITYUTというかっこいいバンドが『エレクトローカル』というイベントをやっていて、それをまた熊本では三本足というバンドが影響を受けて独自の動きをしています。通常のライヴハウスのシステムだと、お客さんを集めることにエネルギーを使ってしまうので、もっと自由にしたいということで、ライヴハウスを借りるのではなく、通常のフラットなクラブのスペースや大学の教室に自分たちで機材を持ち込むスタイルで。そのスタイルに影響を受けて自分たちも機材を揃えてクラブを借りてライヴをやるということを続けています。九州はわりとそういう流れが長崎と大牟田もそういう人が増えてきています。場所代のコストを下げればバックされる金額も若干増えるのでゲストも呼べるし。地域とか熊本を面白くしたいというよりもまず自分たちのモチベーションを上げたいというバンド本位の考え方で、好きなアーティストを呼んでコミュニケーションをとって、刺激をもらっていくというやりかたです。石頭地蔵の場合は、自分がお店をやっていたので東京のMSBRの田野幸治さんから海外のノイズ・アーティストや実験音楽のアーティストを呼ぶので九州でサポートしてくれないかという話が最初で、そこからイベントをスタートして、『PY.KING OF…』というイベントを続けています。DJの子たちを絡めたり、音はぜんぜん違いますけれど同じようなスタンスのバンドもいるので、徐々に広がりつつありますね。
──70年代ロックやポストパンク的な質感で、まだまだこれだけ新しいことができるんだという興奮を感じました。 サウンドの部分で今後目指していることは?
芥川:エフェクターを一切使わず真空管アンプを直で鳴らすということをやってきたので、そこは変わることは今後もないです。ファーストはエンジニアだった人がハードコアが好きだったのでそういうノリのミックスになっていましたが、セカンドに関してはほんとうに素の音をちゃんとしたマイクできれいに録ろうということで、福岡の公共の施設であり、主に演劇用に使われる小ホール(ぽんプラザホール)を一日貸し切って録音しました。今のバンドの音がそのまま素直に録れて、ホール特有の奥行き感のあるサウンドになったと思います。CDを再生する際に音量を上げるとホールのリバーブ感がわかると思いますよ。ギターのアンプも、ファーストはマーシャルとサンのアンプを使ってやってるんですけれど、今回は2台ともフェンダーのアンプを使っているので、かなり音はクリアかつちょっと中域が強い音になっています。ギターもヴィンテージのジャズマスターと80年代のフェンダーのストラトキャスターなので、ギターの音の感触で言えば70年代後半の質感にはなった気がします。ドラムに関してもメイプルの小口径のジャズに使うようなセットで録っているので。楽器類とレコーディングに必要な機材を全て持ち込んで録音しましたが、実際その機材でライヴをしているので、そういった普段行っているライヴの音になっています。サウンドでごまかせるこということがほとんどないので、エフェクターによるダイナミズムではなく、フレージングやコード、リズムを工夫することで楽曲のクオリティを上げたいという考え方、そうでないと楽しくないんです。



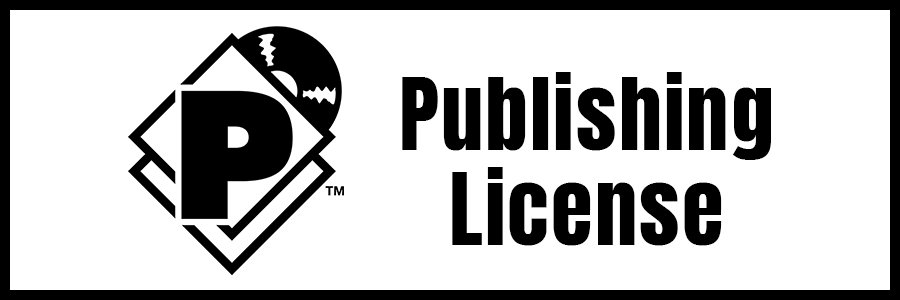










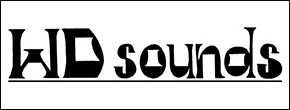
 INSTAGRAM
INSTAGRAM
 X (TWITTER)
X (TWITTER)
 FACEBOOK
FACEBOOK
 TIKTOK
TIKTOK