THE CAT EMPIRE ザ・キャット・エンパイア
OFFICIAL SITE:http://www.thecatempire.com/
LINK:http://www.myspace.com/thecatempire
オーストラリアの壮大な自然と自由な音楽環境は、今まで数多くの素晴らしいルーツ・ロック・バンドを排出してきた。そして、そのバンドの多くは音楽に取り組む姿勢が実にインディペンデントでありながら、必死に働くことは惜しまず、ひたすらライヴを重ねてきて自らの名を広めてきた実績がある。だからこそ、バンドの音楽性もファン層も自然な形で広がり、流行りで終わることなく、新たな魅力を次々と披露している。世界的に成功しているジョン・バトラー・トリオや、ここ日本でも人気を得ているブルー・キング・ブラウン、そしてフェスでの来日で大いにオーディエンスを沸かせてきたザ・ビューティフル・ガールズ、カスタム・キングスやボンジャーなどはもうお馴染みの名前だろう。そんな中、欧米でも絶大な人気を誇るオーストラリアの最後の大物、ザ・キャット・エンパイアが四枚目のフル・アルバム、『シネマ』で遂に日本デビューを果たす。
デビューとは言え、彼らは今まで日本に全く進出してこなかった訳ではない。最初の二枚のアルバム『The Cat Empire』と『Two Shoes』は大型レコード店でも大きな反響を呼び、輸入盤だけにも関わらずヒットとなる。さらに、2006年にはサマーソニックにも出演し、ベスト・アクトの一つとして、今でも記憶に残っている人も多いのではないだろうか。しかし、海外での状況を見ると、まだまだ日本では知られていない存在なのかもしれない。オーストラリア本国ではジョン・バトラー・トリオなどと並んで、国民的バンドの一つに成長しているし、ヨーロッパや北米でも大型フェスを始め、ライヴの動員は大物バンドに引けを取らない人気を誇っている。日本は最後の境地になってしまったかもしれないが、タイミングはこれ以上のものはない。何故なら単独来日も決まっているし、バンド自らがキャリア最高傑作と自信を持って送り出す新作『シネマ』で我々は彼らのことを本格的に知る事が出来るからである。
ステージ上であれ、スタジオの中であれ、ザ・キャット・エンパイアのメッセージは常に、壁を壊していくことであった。それが音楽的なものであろうと、地理的なものや言語の壁であろうと関係ない。しかし、新作の『シネマ』では、彼らはその壁を壊していく行為を今までで最も力強い形で実現しているのは間違いない。彼らの活動の軸であるライヴの壮絶なエネルギーと歓喜のヴァイブスを、ラウンジや裏庭、バーベキューやカフェ、ロード・トリップや世界中のあらゆるパーティー、どのようなシチュエーションにもフィットした形で届けられたアルバムは、リスナーの体も心も踊らせてしまう、まさにバンドが自分たちのピークを捕らえた作品である。一曲目の「Waiting」の躍動感から分かるように、スピーカーを飛び出して、心に入り込む音楽がここにある。
本作では、ザ・キャット・エンパイアの人気を作り上げてきた要素は全て含まれているだけでなく、より大きく、より明るい形で表現されている。レゲエやサルサ、ラテンからヒップ・ホップと様々なジャンルを自由奔放に取り込んできた彼らだが、本作を通して感じられるのはそのサウンドがヴァラエティー豊かなだけでなく、紛れも無く全てがザ・キャット・エンパイアのサウンドなのである。つまり、彼らは自分たちの「声」を発見したわけで、それはここで堂々と披露されている。
「約10年間一緒にステージで演奏してきた結果が、このサウンドを生み出したんだ」と語るのはヴォーカルとパーカッションを担うフェリックス・リーブル。「今までで一番豊かで、それぞれのメンバーの要素が絡み合ったアルバムだと思う。それであって、ザ・キャット・エンパイアという一体感がある。歌詞は少しシリアスになった部分があるかもしれないけど、音楽の高揚感は増したから、不思議なパワーを生み出していると思うんだ。」 彼はこう加えている。「時には考えさせられるけど、時には全てを忘れて踊り狂いたくなる。そんなアルバムだよ。でも今まで一番音的にも色々試したし、表現の幅が広い作品なのは間違いないね。ライヴでこれらの曲をやるのが楽しみでしょうがないよ。特に大きなステージやフェスだと面白そうだね。」
ライヴに対する揺るぎない自信は、彼らがこれまで培ったその数と経験から生まれているのであろう。そしてファッションやハイプで埋め尽くされた昨今の音楽界とは反して、純粋に自分たちのミュージシャンシップと、ステージでの表現力で今やオーストラリアだけでなく、世界中で人気のライヴ・バンドになったという実績にも支えられている。リーブルに加え、トランペットとヴォーカルのハリー・アンガス、キーボードのオリー・マギル、ベースのライアン・モンロー、ドラマーのウィル・ハル・ブラウンとターンテーブルとエフェクトのジャムシッド・カディワラ(akaジャンプス)からなるザ・キャット・エンパイアは昨年アムステルダムで700回目のライブを行い、2010年には800回を迎える。日本のサマーソニックや、ドイツのロック・アム・リング、イギリスのVフェスからアメリカのボナルーという世界中の大型フェスで観客を魅了し、モントリオール・ジャズ・フェスでは数万人を呼び寄せるなど、その実力は確固たるものである。『シネマ』をリリース後はカナダ、アメリカ、ヨーロッパ、イギリスと日本での単独ツアーが予定されている。
前作の『So Many Nights』(2007年)のリリース後、バンド史上最長の8ヶ月も休暇を取り、2009年にはライヴ作品を出しただけであったため、長い間スタジオからも離れていた彼らは、本作に挑む際、リフレッシュした気持ちで作業に入れたと言う。リーブルはこう言う。「休暇を終えて、このアルバムを作るにあたってバンドに戻ってきた時に、このバンドが何故好きなのかを改めて感じられたんだ。初心に戻れたという感覚だったね。期待を良い意味で裏切るようなサウンドを作れて、メンバー間には気持ち良いエネルギーとヴァイブスが流れてて、ライヴがとにかく楽しい楽曲を作れる。そんな大好きな要素を今全部感じている。まるでバンドを始めた頃の感覚に皆戻っていると思うし、それはとてもエキサイティングな気持ちだよ。」
録音スタジオも敢えて地元のメルボルンにあるSing Sing Studioを選び、プロデューサーも地元のスティーヴ・シュラムを起用。メンバー全員が作曲に参加するというルールを設け、結果今まで一番一体感のある作品に仕上がっている。トランペットのハリー・アンガスはこう言う。「バンドに六人もいると、必ずしも全員がライヴでやりたいと言う曲ばかりではない。でも今回は違うね。皆で書き上げた感もあるし、どの曲もライヴでやりたいし、やれる。長い間一緒に演奏してきたから、作曲に参加するのも違和感なかったと思うし、プロデューサーのスティーヴも自然な形で皆を促してくれた。とっても良い流れで作業ができたよ。」ライヴで磨き上げられた演奏力を重視し、スタジオでは機械の力を借りるのではなく、なるべく生のパフォーマンスに近い形で録音。同時に、各曲の持つ感情やムードを皆で探り合い、表現の幅を広めていったという。
どの曲も表情が違いながら、どれもザ・キャット・エンパイア独特の心地良いポップ・センスに染められている。そして気付けばリスナーの心も同じ明るい気持ちになっている、そのような力を持った特別な作品がこの『シネマ』である。タイトル通り、まるで一本の素敵な映画を見た感じになるのである。 そして彼らのライヴもまたその魔法のような力を持っている。2010年11月にはその待望の単独公演がここ日本でも見られることになっているので、是非このアルバムを聴いて、ライヴではバンドと一緒になって盛り上がってもらいたい。



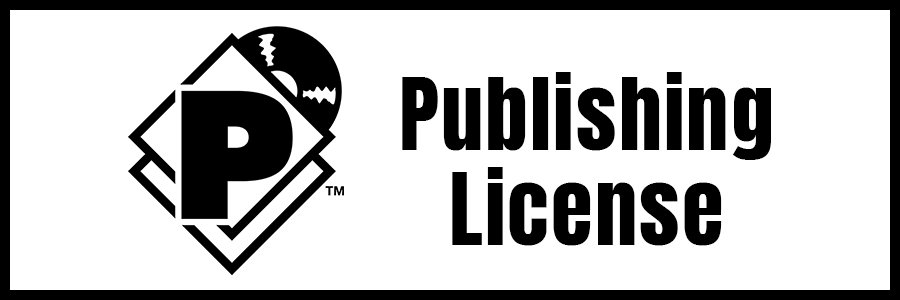










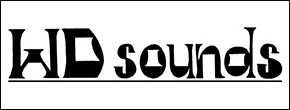
 INSTAGRAM
INSTAGRAM
 X (TWITTER)
X (TWITTER)
 FACEBOOK
FACEBOOK
 TIKTOK
TIKTOK